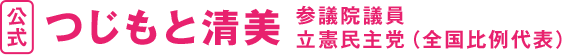●●●「新しい政治の波を起こす起爆剤、接着剤でありたい」(辻元清美)
永田町ガールズは政治を変えるか【第3回】
聞き手=秋山訓子(朝日新聞)
岩波書店『世界』10月号掲載
●党に居場所がなくなった
――七月に社民党を離党されました。
私は参院選で社民党が大きく票を減らしたことに、大きな危機感を持ちました。党を存続させて支持を少しでも増やしていくためにはどうにかして独自色を出していく必要があると思いました。
その一方で私自身は、政権を取るというその一点のために、民・社・国共闘候補となって戦い、国交副大臣として政権の中に入りました。私にとって、自社さ政権に続く二度目の与党経験ですが、いろんな政策を実際に動かすなかで、泥をかぶってでも一ミリでも現実を変えていくことこそ私の政治手法だと強く実感しました。その私のあり方と社民党の今後の方向性にずれを感じ始めていました。変な言い方かもしれませんが、党の中に居場所がなくなった、と感じたんです。
いま私は五〇歳になりました。自分にとって、あと一〇年が政治的な勝負だと思っています。このまま違和感を抱えてやっていくより、残りの人生をかけて、日本の未来のための仕事をするには、自分はどのような立場がいいのか。考えに考えた上で決断しました。だから、いっしょにやってきた社民党のみんなには申し訳ないのだけれど、自分の存在をかけて政治決断をしました。
――市民運動に関わるようになったのは、大学時代からですね。当時、学生運動などもほとんどなく、NGOという言葉もなかったわけですが、きっかけは。
小さい頃大阪で育って在日韓国朝鮮人の差別を見ていたり、中学の社会科の先生が差別や戦争について教えてくれたという背景がありますが、高校三年生のとき名古屋の代々木ゼミナールで小田実さんに会ったことが非常に大きかった。『何でも見てやろう』は読んでいたのですが、小田さんが代ゼミの英語の先生をしていたのです。それで名古屋校での小田さんの講演を聞きに行き、終わって喫茶店で話し込んで意気投合したのです。大学に受かって、上京したのが一九八〇年、二〇歳の時でした。小田さんの市民運動を手伝い始めました。
八〇年代初頭に日本で反核運動がもりあがったとき、代々木公園でビラまきをしていたことがあったんです。その時に公園に行って、土井たか子さんや五島昌子さんが「アジアの女達の会」をやっていると聞いて入りました。
――政治家になろうと思ったことは。
ありませんでした。もちろん政治には関心はありましたが、当時冷戦構造で東西が対立するなかで、市民運動で互いに「反対反対」といってスローガンだけを掲げあう運動には違和感を覚えて、ピースボートを立ち上げたのです。船で東西をジグザグに走らせることで、冷戦の壁に風穴をあけようと思いました。
――ピースボートの活動のなかで、企業や各国といろいろな交渉をするのは、政治のうえでの交渉事と似ているのではないですか。
船をチャーターしようと商船三井客船に訪ねて行ったときは最初、全く相手にされませんでした。いろいろ手を使って大人っぽい人を連れていったり、一〇回行ってやっと門が開いて、それから値段交渉や中身の交渉に入って、船の出港までに五〇回ぐらいは担当の人と会っているんです。船を出した後も各国、特に体制が違う国と入港の交渉するのは、自分の主張だけを言っていても実現しない。反対したり自分の意見を言うだけで終わるのではなくて、物事をクリエイティブに生み出していく、つくり出していくことが世の中を変える原動力になると学びました。これが非常に自分にとっては大きい。
だから何かを実現するためには、どういう方法があるかということを考える。不可能を可能にする手段、それが政治ですよね。国交省の副大臣時代、官僚たちにも言ってきたのですが、できない理由を一〇考えるのではなくて、どうやればできるかということを一〇まず出そうと。
――ピースボートでの経験は与党でも役立ったのですね。船で各国を回るときに、「政治」を感じることは多かったのでは。
八〇年代、西側のフィリピンから東側のベトナムに船を入れるのは、距離は近いのにものすごく大変で交渉が必要だった。そこにベルリンの壁の崩壊があって、大きく時代が変わったんです。その時に人々の運動と政治が不可能を可能に変えていくプロセスを目の当たりにして、政治というものを鮮明に認識しました。その後リオデジャネイロの地球サミット(一九九二年、環境と開発に関する国際連合会議)に行きました。ヨーロッパはNGOが政府の代表団に入って、一緒に地球温暖化問題に取り組んでいる。日本の政治も変えなければと強く意識しました。環境問題で、他の団体と一緒にピースボートもロビー活動で政治家を回ったりするようになりました。
その頃日本にもNPO法をつくろうという機運がでてきました。自社さの村山政権が出来、阪神淡路大震災がおきて、ボランティアはすばやく臨機応変に活動しているのに、行政や政治の出遅れ、不備が非常に目立った。そこで政治を変えねばと再び強く思ったのです。
――その翌年、九六年の総選挙に社民党から出馬しましたね。
土井さんが社民党の党首に戻っていて、「市民の絆」というスローガンを掲げて、女性やNGO、NPOが活躍できる社民党を打ち出しました。そこで私と保坂展人さんと中川とも子さん(現宝塚市長)が九六年一〇月一日、総選挙を目前に土井さんから要請を受けたのです。ピースボートは政治的に中立だったから、出るのはよくないんじゃないかとか悩んで、最終的には筑紫哲也さんに相談したらやってみろと言われて。二日にやりますと返事をして八日から選挙、二〇日に当選という慌ただしさでした。リュックにスニーカー姿で登院しました(笑)。
●与党経験で学んだこと
――当時は自社さ政権で、社民党は与党でした。
このときの与党経験が私の基礎になっています。本当に勉強になりました。まったく何も知らなくて、学校では国会は立法の府って習っていましたから、当時与党だし、じゃあ実際に法律をつくろうとNPO法のプロジェクトチームに入ったのです。今までNPO法をつくるためにロビー活動をしていたところに自分がその中で実現できる立場になったので、楽しくて楽しくて、ゴンゴン進めてたら、自民党の幹事長だった加藤紘一さんに「普段は法律を自分たちでつくってないよ」といわれたんですよ(笑)。
一年生でいきなり最初に議員立法に携わった人は少ない。しかも、あのNPO法は政治家が本当に一から十まで議論してつくりました。NPOという新たなしくみを社会につくる、いわば無から有を生み出す法律でした。なんとか形にするためには、理想的なことばかりいうのではなくて、現実との整合性も考えなければいけない。さらに相手は自民党ですから、NPOや市民は反自民だろう、反体制だろうと誤解している人たちがたくさんいるところが権力を握っていて、そこを突き動かさないといけなかったんです。
――当時の自民党は「ザ・自民党」というお歴々がたくさんいましたね。
自民党が自民党らしかった時ですね。いろいろなことを教わりました。根回しとか調整とか、物事を実現していくにはどうしたらいいか。たとえば、幹事長代理だった野中広務さんには「小さいところを大事にしなければいけない」。政調会長だった山崎拓さんには、やりたいことは実現するまで誰にも言うな、そして「真綿に包んですり足で歩け」と。竹下登さんの「汗は自分でかきましょう、手柄は人に上げましょう」もそうです。私はこれを副大臣のときに常にリフレインしていました。
――その後、辻元さんがさらに名を挙げるのは小泉純一郎総理になってから、国会での「総理、総理」という追及ですね。そして秘書給与の事件があって、議員辞職、逮捕、有罪判決を受けました。
政治というものは不思議で、政治家同士の組み合わせというのがあるんですね。力を発揮したりあるいは異常なまでにハレーションを起こしたり。小泉首相が出てきたときの私や田中真紀子さんが後者だと思う。9・11があって、テロ特措法ができ、日本がアメリカに従って自衛隊がインド洋に派遣されることになった。私は日本が戦争に荷担するんじゃないかという質問をがんがんやった。それであの事件につっこんでいくことになります。
――執行猶予判決を受けましたが、その期間は終了しました。事件をどう総括しますか。
市民運動から政治の世界にきて、素人でした。秘書給与の扱い、事件そのものの間違いは認めます。そのうえで、バブルの辻元清美、メディアにつくられた、その時代の社会の空気を吸って実像以上に虚像が大きくふくらんだ辻元清美があって、それが砕けたという感じです。
――逮捕されて有罪判決まで受け、そして政治の世界に戻ってきた人は希有です。
私は逮捕されて留置場にも入り、裁判で有罪判決を受けました。逮捕の時期も不思議で二〇〇二年三月に辞職して、それから一年以上たった〇三年夏に逮捕され、秋から裁判でした。
裁判の時うれしかったのは、渡部恒三さんが、自分が副議長をやっていた時、辻元はよく仕事をしていたと自ら証人として法廷に立ってくれたんです。辞職中、副議長の公邸に呼んでくれて、励ましてくれた時もありました。おまえはつぶれちゃだめだ、って。そんなに接点はなかったんですが、目をかけていてくれたんですね。
他にも衆議院の職員の方で証人に出ます、と言ってくれた人もいました。三万七〇〇〇筆の署名に、カンパも集まった。私は落ち込んで燃え尽き症候群になって、もう二度と立ち上がれないと思っていた時もありました。
メディアにねらわれるし、もう地元でどんな顔をしていればいいのかわからなくて家にいられず、小さなキャリーバッグを持ち歩いて友達の家を転々としていました。
でも多くの人たちが、もう一回やれと口で言うだけじゃなくて、リスクもかぶりながら思いを託してくれた。それが本当に自分の支えになった。地元の人たちも励ましてくれました。
●政治家の「非常識な決断」
――判決が出た翌二〇〇四年夏の参院選に無所属で大阪選挙区から出馬しました。
判決が出た後、どこか旅行に行きたいと思ったけど、お金がないし自分の身も危ない。その時、私は地元の大阪を全然知らない、と思ったんです。そこで、一ヶ月くらいかけて大阪中を端から端まで全市町村を、リュックを背負って歩いてみた。そうしたら、本当に多くの人が辻元さん元気出せよ、と声をかけてくれたり、食べ物をくれたり、あんなことでへこたれてはあかんで、と言ってくれた。それで自分の体に人間の血が通ってきたというか、もう一度立候補しようかという思いがわいてきて、六年前の参院選でチャレンジしたのです。
小泉さんとの間に決着をつけたいという思いもありました。街に出たら本当にみんな困っている、仕事がなくて仕方なくて公園に毎日来ている。それまで平日の昼間街を歩くことってないでしょう?それで、日本はやっぱりまずいんじゃないかと思った。ちょうどその頃、イラクでの人質事件があって「自己責任」と言う言葉が使われて、すごくおかしいと感じました。そういう思いをどこかで表現したいという思いがふつふつと沸いてあふれでてきたのです。
政治は一種の「自己表現」だと思うんですよ。自分の考えや思いを語って、共感する人と一緒に実現していく。あのとき、私の役割って世の中にとって何だったんだろう、って考えました。そして、スピーカーだ、と思った。小さい声をていねいに拾って、それを大きな声にばあっと広げていく。そういう役割だったのに、私は電源を切られてしまった。だからもう一回、みんなに電源を入れてもらいたいという気持になったんです。
そうはいっても、いざ選挙に出るとなると恐くてね。辞職してから人前に出てないし、悪人扱いされて、犯罪者と言われたし。こんなんで人前に出て演説なんてできるだろうか、って思いました。人が恐いんです。そうしたら私の地元、大阪の島本町町会議員が来て、「選挙をやったほうがいい。やらなかったら辻元さん、死んでしまうで」と背中を押された。でもそれは少数派です。親しかった筑紫さんや田原総一朗さんも意見が半々、ほとんどの人は、まだ若いんだから、執行猶予が終わってから出ればいいと言いました。
でももしそうしていたら、今、私はまだ議員にも復帰していない。その間に衆院選を二回やって、与党になって副大臣になっていますからね。あのときの決断は本当に大きかったし、分かれ道だった。
――ちょうどその頃お目にかかっていますが「参院選に出ようか、どうしよう」とはおっしゃっていましたが、ああもう出るのを決めているんだなというのがわかりました。
政治家というのは、時々「非常識な決断」をするものだと思うんです。自分の信念、思いを貫くために。何を言われても批判を恐れずに。参院選立候補に向けて記者会見する、と発表したとたんに、ありがたいことに選挙のカンパが一五〇〇万くらい集まった。でもその一方で、親しい人から立候補なんかするなんて思わなかった、と言われたり、自分のことしか考えていない、と言われて離れていったりしたこともあります。でも私は、執行猶予の五年間、じっと黙っていることはできない、と思いました。
――決めたら後は一直線だったのですか。
全然(笑)。いざ記者会見したら、その日から何も食べられなくなってしまった。脱水状態になったんです。極度の緊張で体調がおかしくなって、公示の三日くらい前に昔から一緒にやっているメンバーの一人に「私よう出やん、こわい。演説どうすればいいの? 今この階段から落ちて骨折でもするからそしたら引き返せるかしら」って言ったんですよ。そしたら、「じゃあやらんでええやん。ここで寝とり。自分たちが車回して選挙する」って。そこまで言ってくれるのかと。私も何か食べて元気ださなきゃと、その晩ステーキハウスに行ったんです。そしたら食べられた。翌日カラオケボックスに一人で行って演説の練習をして(笑)。それで選挙に突入した。
――しかし選挙は厳しかった。
衆院の地元でもある高槻の駅前で第一声をしたとき、足が震えました。選挙中も、犯罪者と罵声を浴びせられたり、水をかけられたり。あんなつらい選挙、今思い出しても吐き気がしてきます。でも、犯罪者ってヤジがでたら「おまえ自民党のほうがもっとひどいことしてるやろ」って応酬してくれたり、と元気づけられることもたくさんありました。
結果は、約七二万票を取って次点でした。私はあれで息を吹き返したんです。周りは三〇万くらいしか取れないだろう、と言っていました。弟が「姉ちゃんは泥沼に落ちたけど、大勢の人が裁判で助けてくれてひきずりだしてくれた。泥だらけだったけど、七二万の人が泥をふいてくれた。これから歩き出していくんや」と言ってくれた。全国比例のトップが竹中平蔵さんの七二万票でしたから、ほぼ同じだけの票をいただいたのです。その翌年、小泉郵政選挙でたたかい、比例区で復活しました。
――昨年の連立政権樹立では、三党合意で縁の下の力持ちとして動いていましたね。
社民党は小さい政党です。党の主張である憲法9条を守る政治、弱い立場のための政治というのを現実政治のなかでいかに生かせるかをずっと考えてきました。一つのあり方として政権交代後に与党の一角に入ってキャスティングボートを握る。自社さの時はこれです。NPO法や環境アセス法や男女共同参画社会法など、自民党だけではなかなか出来ないことを私たちの力を利用して成立への筋道をつけました。だから私は政権に入ることが政策実現の近道だと思って、黒子的に水面下の交渉をずっとやってきました。
いざ選挙で勝って、連立政権の合意をつくるときも水面下で岡田克也幹事長と、沖縄の基地問題の表現など詰めた。だから今の連立政権には非常に思い入れが強くて、副大臣に任命されてからはJAL再建や中国人個人旅行者ビザの緩和、二三年解決しなかったJRの不採用問題、湯浅誠さんとセーフティネットづくりなどにも取り組みました。
――解決は不可能とさえ思われた不採用問題。どうやって道筋をつけたのでしょう。
私としてはずっと考えていたことで、昨年末に与党幹事長国対委員長の忘年会をやりました。私はまだその時国対委員長でしたから。言い出したのは私。JRと辺野古への基地建設を何とか止めたいという二つのねらいがあったのです。
座が盛り上がったところで、私が「JRの不採用問題は選挙の前に、解決しておいたほうがいいですよね。国交省、つまり政府は今まで国労の人たちと対立してきたから、与党で話し合って、和解案を提示してもらえば、私が政府の立場で受けて合意交渉をできるのでは」と持ちかけたんです。すると、当時民主党の幹事長だった小沢さんが「そうだな、やるか」と。「じゃあみなさん。与党三党でプロジェクト作ってやってください」と話が始まった。辺野古は、「小沢さん、釣り好きやろ? あんなきれいな海、埋め立ててどうするの」と言ったら、小沢さんは「海の埋め立てはあかん」と。
●辺野古移設への歯止め
――結局社民党は普天間移設問題で政権を離脱しましたが、この件でもかなり裏で走り回っておられましたね。
普天間で日米合意はなされましたが、連立三党と沖縄の自治体の合意がなければ進めないと、閣議決定に盛り込んで歯止めにできないかと走り回りました。そうすれば後で何とか足がかりになる。結果的には、日米合意がある限り認められないとなったのですが。
すごく悩みました。でも野党になって、私たちは反対しましたというのと、与党のなかでボロカスに言われても歯止めになる閣議決定を勝ち取るのと、どちらが辺野古新基地建設を止める力になるか考えたのです。今憲法審査会を立ち上がっていないのも与党に社民党がいたからです。自社さの時も私たちが抜けたとたん新ガイドラインやら盗聴法やら国歌国旗法、ダダダッとやられた。その時は筋を通したようにみえても、その後を見たら、間違った方向に行くきっかけを作ることもある。社民党と民主党の選挙協力が崩れたら自民党を利するだけだし、野党として今度は自民党と公明党と協力して政策を提言するのか。そうなると野党の中で行き場がなくて、力が発揮できない。
――自由な立場になって、今後自分の政治家としての役割をどう考えますか。
まずは一人で、もがいてみようと思っています。今の政界は、民主党にも自民党にもそれぞれ集団的自衛権を認めようとか新自由主義的な人もいれば、辺野古移設反対もいれば、ヨーロッパ型の社民主義を目指す人もいる。有権者にとって非常にわかりにくい。各党に散らばって地下水脈のように偏在している「護憲リベラル」の人たちとネットワークして、新しい政治の波が出来ればいい。そのときの起爆剤や接着剤の一人でありたいと思っています。